兵庫県教育委員会事務局 教育企画課 教育企画班
(左)指導主事[現文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付専門職] 中森 慶 (右)班長 粕谷 良介
文部科学省は2024年12月に「被災地学び支援派遣等枠組み」(略称D-EST:Disaster Education Support Team)を構築。被災地に教職員や専門家を派遣し、学校運営や心のケアを支援する仕組みを強化しました。
このD-ESTの原点となったのが、阪神淡路大震災の経験から生まれた、「EARTH(Emergency And Rescue Team by school in Hyogo)」です。今回は、EARTHを所管する兵庫県教育委員会事務局 教育企画課の粕谷良介氏と中森慶氏[現 文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官(施設防災担当)付専門職]に、被災地の教育支援について伺いました。
※本記事は2025年3月に取材したものであり、所属は取材当時のものです。
目次
未曽有の災害から生まれた兵庫県の学校支援チーム「EARTH」
1995年1月17日、兵庫県南部を震源とする阪神・淡路大震災が発生し、最大震度7を観測。未曽有の災害により教育活動の再開が困難な状況の中、県内外から教育関係者による支援が寄せられました。 この経験を次なる災害への備えとするべく、兵庫県教育委員会は同年、防災や避難所運営に関する専門的な知識と実践力を持つ「防災教育推進指導員」の育成を開始。また、1999年に発生したトルコ北西部地震や台湾の集集大地震では、教育委員会事務局職員や教員を現地へ派遣するなど、国際的な支援活動も展開しました。
こうした動きを背景に、2000年4月1日、国内初となる学校支援を目的とした教職員の組織「EARTH」を発足。兵庫県内の教職員90名 と、スクールカウンセラー5名で活動を開始しました。以来、EARTHは全国の被災地において学校再開支援や防災教育の推進に取り組み続けています。
兵庫県から日本各地の自治体へ――広がる支援の輪
2025年3月現在、 EARTHのような学校支援チームがあるのは兵庫県を含めた7道府県。兵庫県と同様に大規模災害を経験し、発災時にEARTHの支援を受けた自治体が大半です。粕谷氏は、「被災した経験を通じて、学校再開や子どもの心のケアの重要性が深く認識されるようになり、それが学校支援チーム発足に繋がっている」と語ります。
全国初の学校支援チームであるEARTHは 、他の学校支援チームのチーム員養成講座への講師派遣や座談会による意見交換などを通じて、これまでに培ったノウハウを共有。また、新たなチーム立ち上げのサポートも行っています。取り組みの波及に尽力する粕谷氏は、災害時の学校支援活動の広がりに期待を示します。「南海トラフ地震など将来的な大規模災害の発生が懸念される中、各地に学校支援チームが設置されることで、災害発生時の対応スピードの向上が見込まれます。各自治体における学校支援チームの存在は今後ますます重要になるでしょう」
能登半島地震におけるEARTHの支援活動
EARTHは能登半島地震発生からわずか4日後の2024年1月5日に現地入りし、支援活動を開始しました。先遣隊として派遣された中森氏は、初動対応を担当。避難所や学校施設の被害状況を把握するとともに、EARTHの活動内容について石川県教育委員会に説明し、必要な支援の把握に努めました。これは、続く本隊の活動を円滑に進めるための基盤を整える、重要なプロセスです。
能登半島地震では道路の寸断により、主要都市である金沢市から派遣先の珠洲市まで片道7時間以上を要するなど、極めてアクセスが困難な状況でした。このため、被災地近郊にホテル等の拠点を確保することができず、メンバーは避難所内で寝袋を使って宿泊しました。 中森氏によれば、「東日本大震災や熊本地震を含むこれまでの支援活動において、拠点を確保できなかった事例は初めて」であり、今回の地震の特殊性を強く印象づけています。実際に、主要都市から150km以上離れた地域が多く被災している上、交通インフラの寸断が復旧活動に著しい困難をもたらしており、地域の地理的孤立性が支援活動のハードルを一層高めている実情が浮き彫りとなっています。
発災後、変化していく支援のかたち
2024年7月、珠洲市教育委員会からの要請を受け、EARTHは再び珠洲市を訪問。震災直後の緊急支援とは異なり、今回は教職員の心のケアが主な活動となりました。災害という特殊な環境は、児童や生徒の心に大きな影響を与えます。集団避難を経験した子とそうでない子の間で心理的な隔たりが生じたり、校庭や体育館が避難所として使用されることで教育活動が制限されたり、ストレスの要因はさまざまです。そんな不安を抱える子どもたちへの適切なケアの方法が分からず、対応に悩む教員は少なくありません。「子どもの前では弱音を吐けない」と感じたり、各自が受けた被害の程度に差があることから、教員同士でも気軽に話ができなかったりと、思いを共有しづらい現実があります。
EARTHはそうした悩みを抱える教職員に対し、安心して話ができる場を提供。テーマをあえて災害に限定せず、フリートーク形式にすることで、無理に言葉を引き出すことなく、自由に語り合える環境づくりを大切にしました。 さらに、子どもの心のケアに関する研修を実施し、教員と子ども双方の不安を和らげるための取り組みも行いました 。中森氏は「先生も被災者である以上、ケアが必要」と語り、傾聴と寄り添う姿勢を支援の軸に据えています。
今後の展望――震災の経験を次代へ繋ぐ
支援活動を経験したEARTH員は、現地から戻った後、子どもたちに被災地の様子や自身が体験したことを伝えます。「ニュースでは伝わりづらい現実も、身近な大人から直接聞くことで、子どもたちはより実感を持って受け止め、記憶にも深く残るようです」と長年教壇に立ってきた中森氏は振り返ります。EARTHの活動は、被災地での支援にとどまらず、子どもたちの防災意識を育む教育にも繋がっているのです。
EARTHの取り組みに共感し、支援活動に携わりたいと考える教職員は、発足から25年が経った現在も数多くいます。毎年開催される養成講座には、2024年は約30名の定員を上回る応募が寄せられました。教職員として阪神・淡路大震災を経験した世代が定年退職などで少しずつ教育現場を離れていく中 、どのように次世代へとノウハウを引き継いでいくかが、今後の支援活動推進の鍵となります。
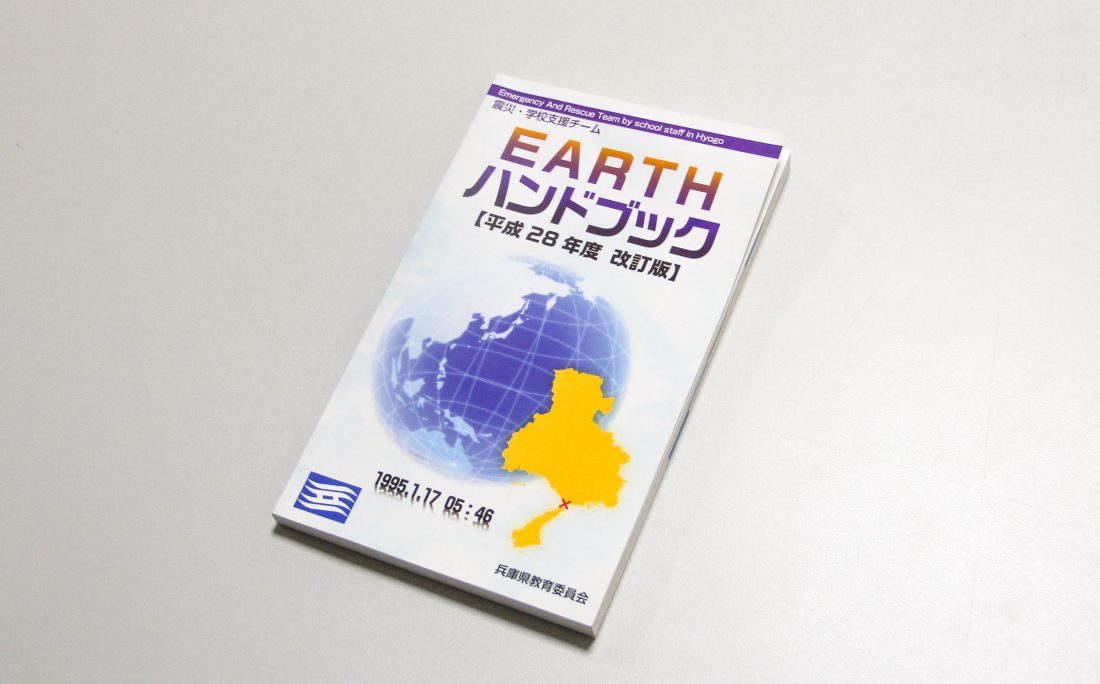
各自治体における学校支援チームの存在は、今後ますます重要になりますが、チームを設けただけでは不十分です。支援体制の整備はもちろん、メンバーに対する継続的な訓練・研修が求められます。EARTHでも、実際に被災地で活動したメンバーが現地で見たこと・感じたことをチーム内で語り継ぎ、次の世代へと受け継いでいます。また、教員が被災地に赴くためには、通常の学校業務を他の教員に任せる必要があり、周囲の理解と協力が欠かせません。被災経験がある兵庫県では比較的理解を得やすい環境にありますが、「他の地域においても、D-ESTや学校支援チームの存在が広がることで、教員が支援に関わりやすくなってほしい」と中森氏は語ります。
災害に強い地域社会を築くには、教育の力が不可欠です。支援に関わることで得た知見を学校現場に還元し、それを次の世代に受け継いでいく。EARTHの取り組みは、そうした循環の中で、未来の防災・減災に貢献しているのです。








 取り組み紹介
取り組み紹介







